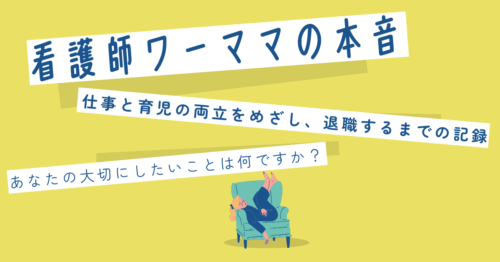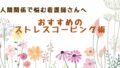こんにちは!たくmamaです😊この記事では、私が18年間務めた職場を退職した体験をお伝えしたいと思います。今まさに「今の職場を辞めたいけど、どうしたらいい😭?」と悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
この記事はこのような看護師さんにおすすめ
- 残業や休日出勤で子どもとの時間が十分にとれなくて、このまま仕事を続けるか迷っている
- 子育てを理由に辞めていいのか悩んでいる
- 職場では様々な役割を担当しているため退職をするのに勇気がいる
《注意⚠️》あくまでもたくmama個人の体験談が多く含まれますので、退職の進め方はご自身の職場の就業規則や環境に応じて対応をしてください。
結論から申しますが「仕事よりもあなた自身・家族を第一優先に考えましょう!あなたが仕事を辞めても代わりはいますが、子どもの父親、母親はあなただけです👪」
退職を決意!退職までのプロセス
私が以前の職場の退職を決めたきっかけは、まさに心身の限界でした。
管理業務、リーダー・メンバー業務、各種委員会の設営など人員不足により多種多様な役割を担い、その結果積み重なる残業(管理職のため手当は無し💦)もしくは家庭に仕事を持ち帰り、休日も夫に子どもを任せ、事務作業(もちろんサービス業務)…。まさに「仕事のために生きている」といった日々が当たり前になっていたのです。

職場全体がサービス業務当たり前。
そのことを誰も疑問に思わない感覚って怖いですね…。
もちろん、家庭の時間は削られ夫婦の関係性も悪くなる一方でした😖これでは「何のために働いているんだろう」と自問自答する日が増えていきました。
その時の状況は関連記事をご覧ください👉

そんな日常に希望を見出せず、退職を決意しました。しかし、退職を決意したとはいえ、実際に職場を離れるまでには、さまざまな手続きや準備が必要です。特に管理職だった私の場合、そのプロセスは想像以上に複雑でした。
私の場合は、以下のステップで退職を進めていきました。
- 退職の意思を上司に報告
- 退職願い、届の作成
- 退職決定後、後任へ引継ぎの準備
- 上司の許可のもと、関連部署や他部署のスタッフに退職を伝えていく
- 自部署の次年度のBSC考案、今年度の成果報告作成
- 後任の者へ引継ぎ、最後の挨拶まわり

特に大変なのが、上司への報告と引継ぎですね。
上司への退職宣言には強い意志と忍耐が必要!
退職を上司に伝える…それはまるで、ラスボス戦のようでした。
私は課長職だったため、部長→副院長→院長といった次々にボスバトルをクリアするように《戦い》とう面接をしなければいけません。私が退職の意向を示したのは年に3回ある定期面談のタイミングでした。

私が退職の理由として伝えたのは「仕事の業務量が多く、家族との時間が取れず関係が悪くなっている。」という一つだけにしました。
『なぜ、一つだけなの?』そう思われた方もいるかもしれませんね。もちろん言いたいことは山のようにありましたが、仕事内容を理由にすると残業の少ない部署への異動や、時短勤務を勧められるのが分かっていたからです。
これは自分自身が部下との面談で退職宣言を受けていた立場だったから予測できたことでした。
だけど実際に異動や時短勤務に変更しても、根本的な改善に繋がらないと確信していました。それは組織の問題もありますが、自分の能力不足や職場への愛情が薄れていたことも理由の一つ。上司からは様々な勤務条件の提案がありましたが「仕事を続けることは家族も反対している」の一点張りで通しました🙅♀️
結果、面接を10回以上(一回の面接に2時間以上かかることも…)繰り返し、退職を認めてもらえました💦

念のためお伝えしておきますが、一般的に社員が退職の意向を示したら、会社側は拒否することはできません。
円満退職につながるポイント
『退職』と聞くと、あなたはどんなイメージを抱きますか? おそらく、「気まずい」「引き止められそう」「職場の雰囲気が悪くなるかも」といった、負の感情が頭をよぎる方も多いのではないでしょうか。定年退職とは異なり、自主退職の場合、お互いが気持ちよく別れるのは難しいと思われがちです。しかし、なるべくネガティブな印象で終わるのではなく、『円満退職』を目指したいと思いませんか?

円満退職とは「上司や同僚の理解を得て、職務の始末を済ませ、互いに気持ちよく退職すること」
【出典】コトバンク:円満退職
私自身、退職を決意しましたが職場への恨みつらみの思いだけではありませんでした。看護師として基礎から育ててもらえたこと、キャリア形成の支援をしてもらえたこと、苦しい時も支えてくれた仲間と出会わせてくれたこと…数多くの感謝の気持ちは間違いなく感じていました。だからこそ、退職を告げる瞬間は本当に胸が締め付けられる思いでした。
「最後は笑顔で、ありがとうと伝えたい」
そんな風に考えるあなたへ、私が実践して効果的だと感じた、円満退職に向けたポイントをお伝えします😊
- 退職の意思は揺るがず、ハッキリ伝える
- お世話になった気持ちは言葉にして伝える
- 「また一緒に働きたい」と思ってもらえる態度で最後まで誠実に対応する
退職の交渉も長期戦になると、次第に疲れや相手への情が出てきて「もう疲れた。会社の条件をのもうかな…」と自分の気持ちが揺らぐこともあります。
でもここで諦めてはいけません!退職が決定するまでは心を揺るがさず、丁寧な言葉で「退職の意思は変わりません」という強い意志を貫きましょう!
無事退職が決まった後はお世話になった方へお礼のあいさつを忘れずにしましょう。私の場合はプチギフトとメッセージカードを添えて一人一人に手渡しました🎁
そして退職に関する手続きは抜けがないように行い、職場に迷惑がかからないようにしましょう。
そして、退職が決まってホッとした時こそ、油断しがちです。 その喜びから、つい人に話してしまうことがあるのですが、これは要注意。職場に影響のない家族や友人なら大丈夫ですが、職場の関係者に話すとどこに情報が漏れてしまうか分かりません。看護の世界では人の人事異動や進退の情報は慎重に扱われます。くれぐれも口外する際は細心の注意を払いましょう⚠
ありがたいことに私が退職した一年後、元上司から「もう一度一緒に働いてみない?」とお声掛けいただいたり、違う元上司からも私の条件に合った転職先を紹介していただき、人との繋がりはとても大切だなと実感しました✨
退職が決まったらやることリスト
『退職が決まった!』ホッとしたのも束の間、次に押し寄せるのは、山のような手続きや引継ぎの準備ですよね。
『何から手をつければいいの?』『抜け漏れがあったらどうしよう…』
そんな不安を感じる方もいるかもしれません。でも、ご安心ください。一つずつ確認していけば大丈夫です。ここでは、退職が決まってからあなたがやるべきこと、知っておくべき手続きについて、内容をまとめてみました!
1.退職届の提出
・就業規則に従って、提出期限を超えないように準備しましょう。
・記載内容はインターネットで検索してテンプレート文を参考にしました。
2.業務の引継ぎ
・後任への引継ぎで内容が多く複雑な場合は、写真や動画などを作成し資料を残すようにしましょう。
・引継ぎが足りないと、退職後も連絡が来ることも…😭後任者がいつでも見直せる形に仕上げるといいでしょう。
3.有給休暇の消化相談
・残っている有休日数を確認し、上司と相談し消化できるよう交渉しましょう。
4.健康保険・年金・雇用保険の手続き
《会社が行ってくれること》
- 健康保険資格喪失証明書の発行
- 雇用保険被保険者の返却
- 源泉徴収票の発行
《自分が行うこと》
- 国民健康保険or家族の扶養に入る手続き(退職後14日以内)
- 国民年金の切り替え(退職後14日以内)
- ハローワークでの失業保険申請(必要時)
退職時忘れがちなこと・見落としがちなこと
✅退職証明書の発行依頼
転職先で求められることがあります。
✅離職票の確認
失業保険を申請する場合に必ず必要となります。
✅源泉徴収票の保管
翌年の確定申告や年末調整に必要になるため、会社から郵送されるので引っ越しの予定がある方は忘れずに新しい住所を伝えておきましょう。
✅会社からの貸与物の返却
ユニフォームやロッカーの鍵、社員証など返却物を確認し、期日までに返却しましょう。
まとめ:自分の大切にしていることを軸に行動を!
「仕事に追われて家族との時間が取れない」
「仕事や家のことばかりで自分を見失いそう」
そう心にモヤモヤを抱えながら過ごされている方は、一度立ち止まって自分の心にそっと問いかけてみてください😌

私にとって何が一番大切だろう?
毎日必死に働いていると、このように考えることが忘れがちになります。大切なことや自分のやりたいことがあるからこそ、仕事も子育ても頑張れるはずです。もちろん退職をすれば自由を手に入れられるかもしれません。しかし、職を失えば収入が減ったり、生活水準が下がるかもしれない…。将来の選択には不安はつきものです。
だからこそ、あなたが「何を大切にしたいか」が明確な軸にあれば、その先の選択肢は絞られ、迷うことなく前に進むことができます。
例えばもし「転職したい」と考えるなら、今の職場に在籍しながら「転職活動」をし、自分の条件に合った職場を探す(転職活動は働きながらでも可能です)退職後すぐに入社できるか相談する。
もし「今の仕事を続けたい」と思うなら、上司に勤務形態の変更を具体的に相談してみるという行動にもつながるでしょう。

人によって「家族」「時間」「お金」「キャリア」など大切なものに違いはあります。
退職だけが全てではありません。答えに応じた人生の選択肢を見つけてみてはいかがでしょうか。
今の人生を変えるのは、他でもないあなた自身の『勇気ある一歩』です🏃!
この記事があなたの背中をそっと後押しできたら幸いです🌸